★The Best Science Books of 2016 (Science Friday)
2016年のベスト・サイエンスブック。
今朝、隣家の人が、外に出て「ダリ、ダリ、ダリ」と声を上げているので目覚めました。
なんだろうと思って聞くでもなく聞いていると、「こっちへおいで」「そっちは危ないよ」など、いろいろなことを言っています。
「そうか、お隣さんではダリを飼ってるのか……あのヒゲを……」
と納得して、再び眠りに落ちようかというところ(なにしろ明け方までお酒を飲んで夜更かししていましたから……)、再び、「ダリ、ダリ、ダリ!」と、今度は先ほどより少し声が大きくなっています。ちょっと苛立ち混じりのような、でもそれを抑えようとしているような、そんな声の調子に聞こえます。
ダリはよっぽど強情な奴なのかな、と思っていると、「ミャーオ」という猫の声。「そう、こっちへおいで!」と呼びかけは続きます。なんだ、猫ちゃんか。
しかし、猫はミャオミャオ言うばかりで、ちっとも呼びかけ主のほうへ寄りつかない様子。私は朦朧とする頭で、「そういえば猫って、呼びかけたらやってくるものなのかしら(犬なら呼ばなくても飛んで来ちゃうけど)」とか、「うちの近所には、猫に紐をつけて散歩をするおじさんがいるなぁ」などとぼんやり連想します。なおも呼びかけが続くなか、「もしかして、隣人殿はその辺の野良猫に名前をつけて呼びかけてるだけなんじゃなかろうか」などと空想が働きもしました。
そうする間にも(って、私はベッドのなかでうだうだしながら空想してただけなんですが)、「ダリ、ほら、こっちだよ」と呼びかけは続きます。「ミャーオ」「ダリ! こっちに来なさい!」
およそ30分近くそんなやりとり(?)があった後で、隣人はとうとう諦めたのか、家へ入ってしまったようでした。相変わらず猫は表で「ミャーオ」と鳴いています。
まさか、お隣さんは猫じゃなくて、なにか別のものに声をかけていたんじゃあるまいか。例えば、ダリとか……そんな空想に頭を占拠されながら、私は再び眠りに落ちたのでありました。
(2013年01月02日、facebookへの投稿から)

★GREEK AND LATIN TEXTS WITH FACING VOCABULARY AND COMMENTARY
「古典ギリシア語とラテン語の語彙と解説つきテキスト」
その名のとおり、古典ギリシア語とラテン語のテキストに語彙と解説をつけた教科書を公開しているサイト。このサイトで公開されているデジタルファイルは無料でアクセスでき、紙版はAmazonで販売されている。
著者はジェフリー・ステッドマン(Geoffrey Steadman)という人で、サイトに掲載された略歴によると、アメリカはオハイオ州の公立高校でラテン語の先生をしている人とのこと。
語学の勉強をどうやって習慣にするかを説いたページから、ちょっとだけそれとなく訳して紹介するとこんなふう。
大学のような環境の外で生涯にわたってラテン語やギリシア語を読みたければ次のようにしよう。
1. 日々達成しやすい目標を設定しよう。
例えば、1日に5行のギリシア語/ラテン語を読む
2. 手の届く範囲で、すぐ目につく場所にテキストを置こう。
3. すでに身についている習慣となっているなにかしらの行動に続けて読む習慣をつなげてみよう。
例えば、バスで座ったとき、コーヒーカップを手にしたとき、ベッドにもぐりこんだとき、など。
(https://geoffreysteadman.com/5-lines-per-day/ から)
どれもシンプルだけれど、本当に重要で、これを実行したら読めるようになると思う。
特に、勉強に使うテキストがモノとしてぱっと目に入るのは肝心。そうでないと、自分で思い出すまで意識がそちらに向かないから。
この場合、デジタルはちょっと不便かもしれない。というのも、普通、デジタルの装置は電源を入れてファイルを呼び出さないと画面に表示されないから。装置がだいぶ優秀になってきたとはいえ、この手間は存外ばかにならない。というのは、本をぱっと手にとってページをめくる手軽さと比べてみると実感できる。
ここから考えると、こんなアプリを考えられる。例えば、ユーザーが一定範囲内に近づくと自動で起動して画面に読むべきテキストを表示する。
これなら目につくところに本が置かれてあるのと似た状態にできそう。この点、本は依然としてとても便利。
3について、私は考えたことがなかったけれど、言われてみたら納得。ある動作に別の動作を関連づけるわけです。AをしたらBという連想が働くように自分を訓練するということだけれど、肝心なことはすでに自分がよく繰り返す動作に関連づけよといっているところかと思う。
とにかく語学は繰り返すことでしか身につかないので、どうやって勉強を習慣にできるかが、実は最大のコツかもしれない。
年始の挨拶とともに届いたゲラを見ることからスタート。
(文筆職人の仕事始めははやい)
思えば20年くらい前にコーエーでゲームをつくりながらああでもないこうでもないと考えたことを20年越しでようやっと言葉にできた、という感じの文章であります。
詳しくはこの文章が掲載される本の刊行時にお知らせしたいと思います。
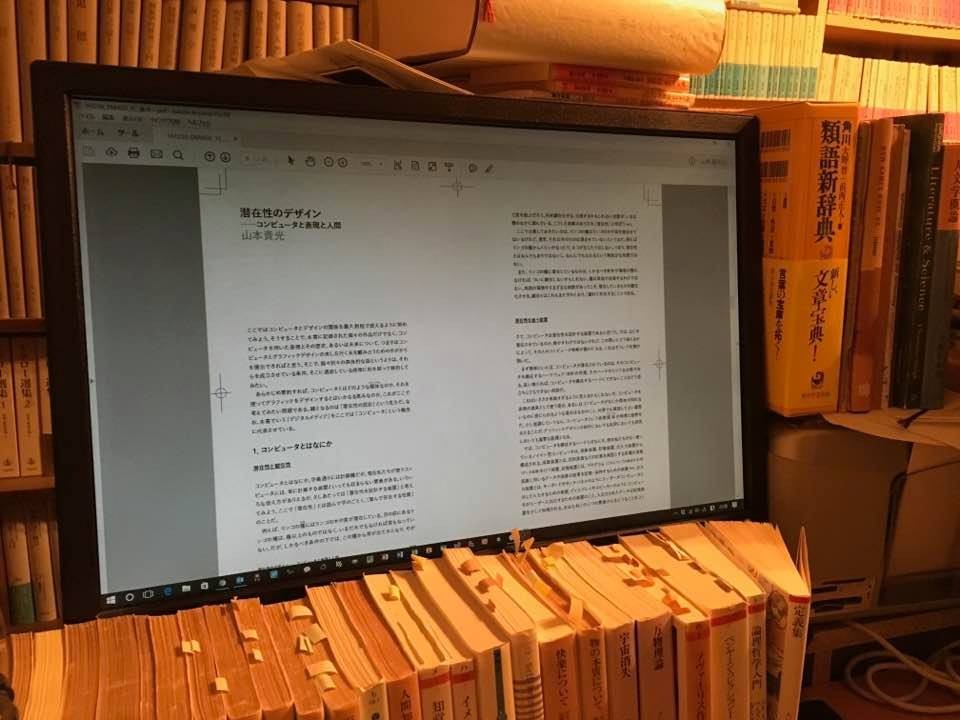
本を買うつもりはなかったんです。たまさか通りがかった池袋で三省堂書店が開いていたから……
右上の『科学史へのいざない』は本日届いた古本。
背後に立っているのは2016年年末に入手した本。
今年も年末にゲンロンカフェで斎藤哲也さん、吉川浩満くんと人文書総まくり鼎談があるかもしれないので、そのつどしっかり記録しておこう(人それを捕らぬ狸の皮算用という)。

末尾になりましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
みなさま、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。
書いている当人以外にはほとんど意味のない、私的な、あまりに私的な2016年の回顧と2017年の展望のコーナーです。
2016年は懸案だった『脳がわかれば心がわかるか――脳科学リテラシー養成講座』(吉川浩満との共著、太田出版)と『「百学連環」を読む』(三省堂)の2冊を刊行できました。これに関連して対談やブックフェアなどの各種イヴェントも開催していただきました。ご尽力、ご参加いただいたみなさまに感謝いたします。
輪をかけてどうでもよいことですが、前者は共著を含めて小生10冊目の本となりました。翻訳書も含めるとこれまで都合14冊の本を刊行した計算であります。2004年に最初の著書『心脳問題――「脳の世紀」を生き抜く』(吉川浩満と共著、朝日出版社)を刊行してから12年が経ちましたので、平均すると年に1冊程度ということになりましょうか。といっても、とりたてノルマや目標があるわけではなく、たまさかそうした機会が巡ってきた折りに書いているというのが実情であります。
なぜこんなことが気になったかというと、先日、外山滋比古さんにお話を聞く機会があり、事前の準備として氏の著作一覧を眺めたところ、その数は優に100を超えています。いったいどうするとそんなにたくさんの本をつくれるのか、とおおいに魂消るということがあったのでした。1冊ごとに七転八倒している身としては、その筆の速さに驚くばかりです。
先日、池上彰さんと佐藤優さんの読書にかんする対談本を読みましたが、このお二人もたくさんの著作がおありですね。100冊以上の著書のある人物をリストにするとどうなるだろうかと、どうでもよいことを思ったりして。山ほど本を書いているというと私が思い出すのは徳富蘇峰です。あ、外山さんとのお話は、年明けの『週刊読書人』に掲載される予定です。
自分の著作一覧を眺めると、われながら訳がわからないラインナップですが、これからもますます訳がわからなくなるよう務めたいという思いを新たにしたことでありました。
さて、2016年の回顧に戻りますと(え、もういい?)、「ゲンロンβ」で吉川くんと書評対談「人文的、あまりに人文的」の連載を始めたのも今年のことでした。毎回2冊の人文書をとりあげてああでもないこうでもないとざっくばらんに議論する対談です。先日第9回を書いたところで、連載を始めたのもなんだか遠い昔のことのような気がいたします。
ところで東浩紀さんが編集長を務める「ゲンロンβ」と、荻上チキさんが編集長の「αシノドス」は――偶然かつどちらでもよろしいことですが、両誌ともギリシア文字が入っていますネ――この値段でこんなに読めてよいのだろうかと、少々不安になるくらい毎号充実しています。未読の方は、一度お試しあれ。
季刊『考える人』(新潮社)に3回連続で掲載した、これまた吉川くんとの対談「生き延びるための人文」もそうですが、なにかと「人文(humanities)」について考えることの多い年でもありました。
講義や講演の方面では、寄藤文平さんと2人で担当しているミームデザイン学校での講義が自分にとっても未知の領域ということもあってたいへん新鮮です。モブキャストでは、講師として研修を行うことに加えて、久しぶりに商業用ゲームの企画書も何本か書きました。ゲームについては、引き続き機会があるつど考えて参りたいと思います。
さまざまな原稿や講演等のご依頼をいただき、ありがとうございました。そんな機会でもなかったら自分では考えなかったかもしれなかったことを考える時間ときっかけを頂戴しました。
2016年の仕事については下記エントリーにまとめてみましたので、うっかり関心をもってしまった方はご笑覧くださいませ。
2017年は何冊かの本を形にしたいと念じております。順不同でいくつかの予定をご紹介します。
★『夏目漱石『文学論』論(仮)』(幻戯書房)
もう何年同じことを言ってるのかという状態で恐縮ですが、次はこの本を完成させる所存で目下鋭意追い込み中です。漱石の悪名高き『文学論』を使える道具に仕立て直そうという目論見であります。
★『人工知能入門(仮)』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)
2016年に『人工知能のための哲学塾』をはじめ矢継ぎ早に人工知能関連書を刊行した三宅陽一郎さんとともに、ちくまプリマー新書の1冊として共著を準備中です。
★『科学の文体(仮)』(講談社ブルーバックス)
古今の科学論文や科学書を題材に、なにがどのように書かれているのかを、『文体の科学』(新潮社)で論じた意味での「文体」の観点から眺め、検討してみようという主旨でございます。この方面については、これとは別に大きな本になりそうな企画も準備中。
★マリー・セットガスト『先史学者プラトン(仮)』(吉川浩満との共著、朝日出版社)
これまた何年かやってるのかという翻訳ですが、2017年こそ刊行にこぎつけます。吉川くんとはもう1冊、思想史方面の面白い翻訳にも取り組み中。
★『生き延びるための人文(仮)』(吉川浩満との共著、新潮社)
『考える人』に3回連載した対談をもとに本をつくる予定です。吉川くんとは、これも数年越しになってしまった構想中の本がもう1冊あり、進めて参る所存です。
以上のほか、何冊かの企画を準備しております。
年明けには『週刊読書人』(「回顧篇」で触れた外山滋比古さんとのお話)、『現代思想』(美しいセオリー)、『ユリイカ』(ソーシャルゲーム)、『世界思想』その他に文章が掲載される予定です。また、ウェブでの連載も準備中。これらは改めて当ブログでご案内したいと思います。
2016年に続いて株式会社モブキャストとのプロ契約を更新しました。東京工芸大学、代々木高等学院、ミームデザイン学校での講義も引き続き担当する予定です。
個人的にあたためているゲームやソフトウェアのアイディアを形にしたいのですが、最大のモンダイはどうやって時間を捻出するかでしょうか。つべこべ言わずにコツコツこしらえたいと思います。
なによりもここ数年、以前にもまして勉強できていないのが困ります。勉強します、しますとも。
2017年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
みなさま、よいお年を。
先日のゲンロンカフェでの鼎談では、2016年の人文書(2015年12月から2016年11月までに刊行された人文書)をご紹介しました。
ここでは2016年に出会った本から印象に残ったものをご紹介します。つまり、刊行年に関係なく、今年読んだ本からというわけです。ただし、ゲンロンカフェで配布したリストに入れたものは入れていません。
少しずつ更新します。
■芸術
★北澤憲昭+森仁史+佐藤道信編『美術の日本近現代史――制度・言説・造型』(東京美術、2014/01)
日本において西洋風の美術・芸術を移入するにあたり、言説や制度の側ではどのような試みや議論があったのか、という関心から手にした本。学術の各方面について同様の本があれば読みたいと思います。
続きを読む
2012年12月29日にfacebookに投稿した文章。
facebookは「n年前の今日、あなたはこんな投稿をしましたよ」てな具合に自分の投稿を表示する機能があって、書いたまま忘れていたものを見せてくれます。
――――――――――
小澤京子先生のメールの書き出しに関する投稿に触発されて、棚から『ベンヤミン著作集』の書簡の巻を取り出して、書き出しばかり眺めてみたら、これがなんだか面白い。
a. 「きみになんぞ、手紙を書くいわれはないんだがな。」
冒頭からツンデレ全開。
b. 「ぼくには以前から道徳上のアキレス腱がひとつある。」
冒頭から中二病全開。
c. 「今日の午前は講義がないので、手紙をいくつか書くつもりだ。まずきみへのから。」
「お前さんの事情なんか知らないよ」と思わせておいて、第二文で一気に懐に入り込む高等テクニック。
d. 「カルラさん――ぼくは王立図書館の「専門研究者用」の読書室で、数冊の本をまわりに積み上げて、これを書いています。」
cの応用編と思われるが、惜しいことに続く第二文が省略されてしまっている。おそらくc以上に高度な(略
e. 「ぼくはこの手紙をもって完全に、なんの留保もなしに、あなたと絶縁しますが、どうかこの手紙を最後の誠意のあかしとして、それ以外の何ものでもないものとして、受けとってください。」
言いたいことをズバっと表明することから始める潔いスタイル。絶縁と誠意が一つの文のなかに、こんなふうに並ぶこともできる。
f. 「手紙は嬉しかった。」
飾らない書き出し。文脈を選ばず今日から使える。ただし、eのような手紙をもらった場合には慎重を要する。
いやあ、参考になりますネ。
――――――――――
出典は『ヴァルター・ベンヤミン著作集』第14巻(晶文社、1975)でした。品切れ中かな。
小澤京子先生の新たなご著書が現れる日も楽しみに待っております。